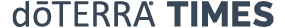- フリーワードで検索する
- 製品別で検索する
- 動画
SNS検索
-
 2015.03.26
2015.03.26新学期、新年度を前に、新しい生活の準備をされている方も多い…
 新学期、新年度を前に、新しい生活の
新学期、新年度を前に、新しい生活の
準備をされている方も多いこの時期。
香りを活用したお部屋クリーニングで
フレッシュなスタートを切りませんか?
ドテラのサンリズムは、
オレンジやレモン、グレープフルーツ、
マンダリン、ベルガモットなど
太陽の恵みをいっぱい浴びた
フレッシュな柑橘類の香りに、
バニラビーンズの甘い香りが加わった
まさに「元気の出る」香り♪
そのオイルをバケツに2~3滴入れ、
あとは普通の水拭きと同様に
固く絞った雑巾で部屋中を拭き掃除♪♪
スプレーボトルに水と数滴のオイルを
加え、窓掃除をするのもいいですね。
春の爽やかな風に乗って、サンリズムの
香りが部屋中に広がりますよ。
気持ちも明るく、前向きに!
新生活、がんばりましょうp(*^-^*)q2015/03/26 08:00:02 -
 2015.03.25
2015.03.251日のはじまりはたっぷりの朝日とウィンドリズムの香りで(^-^)ノ

-
 2015.03.25
2015.03.251日のはじまりはたっぷりの朝日とウィンドリズムの香りで(^-^)ノ

-
 2015.03.25
2015.03.251日のはじまりはたっぷりの朝日とウィンドリズムの香りで(^-^)ノ

-
 2015.03.24
2015.03.24◇◆◇◆━dōTERRA ABC ⑧━◆◇◆◇【日本の香り文化】エッセンシャルオイ…
 ◇◆◇◆━dōTERRA ABC ⑧━◆◇◆◇
◇◆◇◆━dōTERRA ABC ⑧━◆◇◆◇
【日本の香り文化】
エッセンシャルオイルは、西洋から
入ってきたものですが、日本でも古来より
香りを楽しむ文化がありました。
日本独自の香りの文化といえば
500年前頃に確立した「香道」ですが、
この香道で使用される香木について
最初に史料に残されたのは6世紀頃のこと。
日本最古の歴史書である「日本書記」に、
淡路島の浜に漂着した大木で島の人が
焚火をしたところ、大変よい香りがして
朝廷に献上したという記述があります。
ただ、それ以前から香木や香りの文化は
仏教と共に日本へ伝えられていたそう。
仏教が誕生したインドでは、
仏教儀式で使われる香りや薬として
香料を使う風習があり、それが中国経由で
日本に伝えられたと考えられています。
平安時代に入ると、香りは仏前に
供えるだけでなく、部屋に漂わせたり、
衣装にたきしめるなど、貴族たちによって
生活の中で楽しむものとなっていきます。
香りを組み合わせて、その優劣を競い合う
「香合わせ」という遊びを当時の貴族達が
たしなんだことも、「源氏物語」などの
文学を通じて知ることができます。
やがて室町時代に入ると、茶道などの
芸事と共に、一定の作法で香を鑑賞する
「香道」という芸道として確立されます。
さらに、江戸時代になると国内で初めて
線香が製造され、香油入りの化粧品が
流行するなど、香りの文化は一気に
庶民へと広まっていきました。
そして明治時代に入ると、フランス製の
香水が「舶来物」として紹介され、
国家による文明開化政策もあいまって、
香水や化粧品など、西洋風の香り文化が
広まっていくことになるのです。
このように、日本でも昔から
生活の中で親しまれてきた香り。
エッセンシャルオイルでお馴染みの
フランキンセンスやミルラ、シナモンは
「乳香」「没薬」「桂皮」として
香道でもよく用いられる天然香料です。
香りの文化は知らず知らずのうちに
日本人のDNAに刻み込まれ、刺激を
受けているのかもしれませんね(*^-゚)
いかがでしたか?
次回の「dōTERRA ABC」もお楽しみに♪2015/03/24 08:00:01 -
 2015.03.24
2015.03.24◇◆◇◆━dōTERRA ABC ⑧━◆◇◆◇【日本の香り文化】エッセンシャルオイ…
 ◇◆◇◆━dōTERRA ABC ⑧━◆◇◆◇
◇◆◇◆━dōTERRA ABC ⑧━◆◇◆◇
【日本の香り文化】
エッセンシャルオイルは、西洋から
入ってきたものですが、日本でも古来より
香りを楽しむ文化がありました。
日本独自の香りの文化といえば
500年前頃に確立した「香道」ですが、
この香道で使用される香木について
最初に史料に残されたのは6世紀頃のこと。
日本最古の歴史書である「日本書記」に、
淡路島の浜に漂着した大木で島の人が
焚火をしたところ、大変よい香りがして
朝廷に献上したという記述があります。
ただ、それ以前から香木や香りの文化は
仏教と共に日本へ伝えられていたそう。
仏教が誕生したインドでは、
仏教儀式で使われる香りや薬として
香料を使う風習があり、それが中国経由で
日本に伝えられたと考えられています。
平安時代に入ると、香りは仏前に
供えるだけでなく、部屋に漂わせたり、
衣装にたきしめるなど、貴族たちによって
生活の中で楽しむものとなっていきます。
香りを組み合わせて、その優劣を競い合う
「香合わせ」という遊びを当時の貴族達が
たしなんだことも、「源氏物語」などの
文学を通じて知ることができます。
やがて室町時代に入ると、茶道などの
芸事と共に、一定の作法で香を鑑賞する
「香道」という芸道として確立されます。
さらに、江戸時代になると国内で初めて
線香が製造され、香油入りの化粧品が
流行するなど、香りの文化は一気に
庶民へと広まっていきました。
そして明治時代に入ると、フランス製の
香水が「舶来物」として紹介され、
国家による文明開化政策もあいまって、
香水や化粧品など、西洋風の香り文化が
広まっていくことになるのです。
このように、日本でも昔から
生活の中で親しまれてきた香り。
エッセンシャルオイルでお馴染みの
フランキンセンスやミルラ、シナモンは
「乳香」「没薬」「桂皮」として
香道でもよく用いられる天然香料です。
香りの文化は知らず知らずのうちに
日本人のDNAに刻み込まれ、刺激を
受けているのかもしれませんね(*^-゚)
いかがでしたか?
次回の「dōTERRA ABC」もお楽しみに♪2015/03/24 08:00:01 -
 2015.03.24
2015.03.24◇◆◇◆━dōTERRA ABC ⑧━◆◇◆◇【日本の香り文化】エッセンシャルオイ…
 ◇◆◇◆━dōTERRA ABC ⑧━◆◇◆◇
◇◆◇◆━dōTERRA ABC ⑧━◆◇◆◇
【日本の香り文化】
エッセンシャルオイルは、西洋から
入ってきたものですが、日本でも古来より
香りを楽しむ文化がありました。
日本独自の香りの文化といえば
500年前頃に確立した「香道」ですが、
この香道で使用される香木について
最初に史料に残されたのは6世紀頃のこと。
日本最古の歴史書である「日本書記」に、
淡路島の浜に漂着した大木で島の人が
焚火をしたところ、大変よい香りがして
朝廷に献上したという記述があります。
ただ、それ以前から香木や香りの文化は
仏教と共に日本へ伝えられていたそう。
仏教が誕生したインドでは、
仏教儀式で使われる香りや薬として
香料を使う風習があり、それが中国経由で
日本に伝えられたと考えられています。
平安時代に入ると、香りは仏前に
供えるだけでなく、部屋に漂わせたり、
衣装にたきしめるなど、貴族たちによって
生活の中で楽しむものとなっていきます。
香りを組み合わせて、その優劣を競い合う
「香合わせ」という遊びを当時の貴族達が
たしなんだことも、「源氏物語」などの
文学を通じて知ることができます。
やがて室町時代に入ると、茶道などの
芸事と共に、一定の作法で香を鑑賞する
「香道」という芸道として確立されます。
さらに、江戸時代になると国内で初めて
線香が製造され、香油入りの化粧品が
流行するなど、香りの文化は一気に
庶民へと広まっていきました。
そして明治時代に入ると、フランス製の
香水が「舶来物」として紹介され、
国家による文明開化政策もあいまって、
香水や化粧品など、西洋風の香り文化が
広まっていくことになるのです。
このように、日本でも昔から
生活の中で親しまれてきた香り。
エッセンシャルオイルでお馴染みの
フランキンセンスやミルラ、シナモンは
「乳香」「没薬」「桂皮」として
香道でもよく用いられる天然香料です。
香りの文化は知らず知らずのうちに
日本人のDNAに刻み込まれ、刺激を
受けているのかもしれませんね(*^-゚)
いかがでしたか?
次回の「dōTERRA ABC」もお楽しみに♪2015/03/24 08:00:01 -
 2015.03.23
2015.03.23【Herbal tips ハーブのお話】◇ラベンダー◇紀元前より世界各地…
 【Herbal tips ハーブのお話】
【Herbal tips ハーブのお話】
◇ラベンダー◇
紀元前より世界各地で愛され、
「ハーブの女王」というニックネーム
まで持つラベンダー。
その愛される理由は、なんといっても
香り。古代ローマやギリシャの貴族は、
バスタブが紫色に染まるほどラベンダーを
浮かべ、安らぎの香りを楽しみながらの
入浴を好んだそうです。
また中世のイギリスでは、貴婦人たちに
ラベンダー水が愛用されていたという
記録が残っています。チャールズ1世の妃
ヘンリエッタ・マリアもラベンダーを
こよなく愛し、ラベンダーの香水を使い、
ラベンダーを練り込んだお菓子が大好物
だったとか('-'*) ラベンダーの香りが
動乱の時代に生きた人々の
心を癒していたのかもしれませんね。
貴族を中心に愛用されたラベンダーですが
ヨーロッパでは、虫が嫌う香りとして
知られ、一般にも利用されていました。
イタリアでは、ラベンダーの花の茂みに
洗濯物を広げて香りを染み込ませ、
虫除けにしたそう。
乾燥させたラベンダーをポプリにして
タンスなどに入れ、良い香りを
衣類に移すという習慣は、現代にも
残っていますね。これはラベンダーの
エッセンシャルオイルを使った
匂い袋でも真似できます☆
ハーブのトリビア、いかがでしたか?
次回もお楽しみに♪2015/03/23 08:00:02 -
 2015.03.23
2015.03.23【Herbal tips ハーブのお話】◇ラベンダー◇紀元前より世界各地…
 【Herbal tips ハーブのお話】
【Herbal tips ハーブのお話】
◇ラベンダー◇
紀元前より世界各地で愛され、
「ハーブの女王」というニックネーム
まで持つラベンダー。
その愛される理由は、なんといっても
香り。古代ローマやギリシャの貴族は、
バスタブが紫色に染まるほどラベンダーを
浮かべ、安らぎの香りを楽しみながらの
入浴を好んだそうです。
また中世のイギリスでは、貴婦人たちに
ラベンダー水が愛用されていたという
記録が残っています。チャールズ1世の妃
ヘンリエッタ・マリアもラベンダーを
こよなく愛し、ラベンダーの香水を使い、
ラベンダーを練り込んだお菓子が大好物
だったとか('-'*) ラベンダーの香りが
動乱の時代に生きた人々の
心を癒していたのかもしれませんね。
貴族を中心に愛用されたラベンダーですが
ヨーロッパでは、虫が嫌う香りとして
知られ、一般にも利用されていました。
イタリアでは、ラベンダーの花の茂みに
洗濯物を広げて香りを染み込ませ、
虫除けにしたそう。
乾燥させたラベンダーをポプリにして
タンスなどに入れ、良い香りを
衣類に移すという習慣は、現代にも
残っていますね。これはラベンダーの
エッセンシャルオイルを使った
匂い袋でも真似できます☆
ハーブのトリビア、いかがでしたか?
次回もお楽しみに♪2015/03/23 08:00:02 -
 2015.03.23
2015.03.23【Herbal tips ハーブのお話】◇ラベンダー◇紀元前より世界各地…
 【Herbal tips ハーブのお話】
【Herbal tips ハーブのお話】
◇ラベンダー◇
紀元前より世界各地で愛され、
「ハーブの女王」というニックネーム
まで持つラベンダー。
その愛される理由は、なんといっても
香り。古代ローマやギリシャの貴族は、
バスタブが紫色に染まるほどラベンダーを
浮かべ、安らぎの香りを楽しみながらの
入浴を好んだそうです。
また中世のイギリスでは、貴婦人たちに
ラベンダー水が愛用されていたという
記録が残っています。チャールズ1世の妃
ヘンリエッタ・マリアもラベンダーを
こよなく愛し、ラベンダーの香水を使い、
ラベンダーを練り込んだお菓子が大好物
だったとか('-'*) ラベンダーの香りが
動乱の時代に生きた人々の
心を癒していたのかもしれませんね。
貴族を中心に愛用されたラベンダーですが
ヨーロッパでは、虫が嫌う香りとして
知られ、一般にも利用されていました。
イタリアでは、ラベンダーの花の茂みに
洗濯物を広げて香りを染み込ませ、
虫除けにしたそう。
乾燥させたラベンダーをポプリにして
タンスなどに入れ、良い香りを
衣類に移すという習慣は、現代にも
残っていますね。これはラベンダーの
エッセンシャルオイルを使った
匂い袋でも真似できます☆
ハーブのトリビア、いかがでしたか?
次回もお楽しみに♪2015/03/23 08:00:02 -
 2015.03.20
2015.03.20★☆★dōTERRA流!ご当地グルメ★☆★第5回 呉汁(全国)* … * … * …
 ★☆★dōTERRA流!ご当地グルメ★☆★
★☆★dōTERRA流!ご当地グルメ★☆★
第5回 呉汁(全国)
* … * … * … * …* … * … * … * …*
日本各地で愛されている郷土料理や
話題のB級グルメを自宅で簡単Cooking♪♪♪
ドテラのエッセンシャルオイルを
プラスして、さらに美味しく召し上がれ☆
* … * … * … * …* … * … * … * …*
「呉汁(ごじる)」をご存じですか?
水に浸して柔らかくなった大豆を
すり潰したものを「呉」といいます。
呉汁は、それを汁に入れて野菜や肉などと
共に煮込んだ料理。全国各地で昔から
親しまれている郷土料理です。
現在はあまり食べられなくなりましたが
埼玉県の川島町など、地域のソウルフード
として、呉汁を見直す動きも!
野菜たっぷりで、大豆イソフラボンも
摂れる呉汁は女性に嬉しい一品。
さらに、ドテラのジンジャーオイルを
加えれば、身体の芯からポカポカする
無敵のメニューになりますよ!
<材料>(4人分)
大豆(水で戻した後) 300g
ごぼう 1/2本
にんじん 1/2本
だいこん 1/4本
里いも 4個
さつまいも 1/4本
かぼちゃ 1/8個
しめじ 40g
しいたけ 4個
水菜または小松菜 1束
長ねぎ 1/2本
※野菜は冷蔵庫の残り物の野菜でもOK
豚肉または鶏肉(お好みで) 約200g
うどん 4玉(800g)
ドテラジンジャーオイル お好みで2~3滴
【うどんつゆ】
だし汁 1500㏄
醤油 大さじ6
みりん 大さじ2
塩 小さじ2
<作り方>
1.水に浸して柔らかくなった大豆を
フードプロセッサなどで小さな粒が残る
程度につぶしてペースト状に。
2.【うどんつゆ】の材料を鍋に入れて
火にかけ、水菜や長ねぎ以外の野菜を
加えて煮る。
3.2に火が通ったら、1のペースト、
うどん、肉、残りの野菜を入れて
10分ほど煮る。
※この時、大豆の泡がプクプク出て
きたら優しく混ぜること。
4.最後にジンジャーオイルをお好みで
加減をしながら垂らせば完成!
大豆のやさしい味わいを、ジンジャーの
風味がピリッと引きしめて、食が進むこと
間違いなし!
栄養満点の呉汁。お住まいの地域でも
郷土料理として伝わっているかも!?
ぜひお試しくださいね♪2015/03/20 08:00:02 -
 2015.03.20
2015.03.20★☆★dōTERRA流!ご当地グルメ★☆★第5回 呉汁(全国)* … * … * …
 ★☆★dōTERRA流!ご当地グルメ★☆★
★☆★dōTERRA流!ご当地グルメ★☆★
第5回 呉汁(全国)
* … * … * … * …* … * … * … * …*
日本各地で愛されている郷土料理や
話題のB級グルメを自宅で簡単Cooking♪♪♪
ドテラのエッセンシャルオイルを
プラスして、さらに美味しく召し上がれ☆
* … * … * … * …* … * … * … * …*
「呉汁(ごじる)」をご存じですか?
水に浸して柔らかくなった大豆を
すり潰したものを「呉」といいます。
呉汁は、それを汁に入れて野菜や肉などと
共に煮込んだ料理。全国各地で昔から
親しまれている郷土料理です。
現在はあまり食べられなくなりましたが
埼玉県の川島町など、地域のソウルフード
として、呉汁を見直す動きも!
野菜たっぷりで、大豆イソフラボンも
摂れる呉汁は女性に嬉しい一品。
さらに、ドテラのジンジャーオイルを
加えれば、身体の芯からポカポカする
無敵のメニューになりますよ!
<材料>(4人分)
大豆(水で戻した後) 300g
ごぼう 1/2本
にんじん 1/2本
だいこん 1/4本
里いも 4個
さつまいも 1/4本
かぼちゃ 1/8個
しめじ 40g
しいたけ 4個
水菜または小松菜 1束
長ねぎ 1/2本
※野菜は冷蔵庫の残り物の野菜でもOK
豚肉または鶏肉(お好みで) 約200g
うどん 4玉(800g)
ドテラジンジャーオイル お好みで2~3滴
【うどんつゆ】
だし汁 1500㏄
醤油 大さじ6
みりん 大さじ2
塩 小さじ2
<作り方>
1.水に浸して柔らかくなった大豆を
フードプロセッサなどで小さな粒が残る
程度につぶしてペースト状に。
2.【うどんつゆ】の材料を鍋に入れて
火にかけ、水菜や長ねぎ以外の野菜を
加えて煮る。
3.2に火が通ったら、1のペースト、
うどん、肉、残りの野菜を入れて
10分ほど煮る。
※この時、大豆の泡がプクプク出て
きたら優しく混ぜること。
4.最後にジンジャーオイルをお好みで
加減をしながら垂らせば完成!
大豆のやさしい味わいを、ジンジャーの
風味がピリッと引きしめて、食が進むこと
間違いなし!
栄養満点の呉汁。お住まいの地域でも
郷土料理として伝わっているかも!?
ぜひお試しくださいね♪2015/03/20 08:00:02